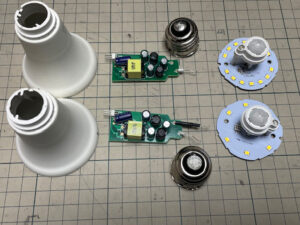かなり使い続けている扇風機、K-C308G。
メインの入り切りスイッチが動作しにくくなっていて、それでもだましだまし使って30年前後。
さすがに電源操作がほとんどできなくなってきたので、ようやく重い腰を上げ修理することにした。
おそらくはスイッチが動作限界だったんだろうと当たりを付け、底部から分解。
簡単に基板にアクセス。
抵抗部分が焼け気味なのが大変気になるが、スイッチを探す。
メインのタクトスイッチを外してテスターで当たると、やはり動作不良。
かつては使っていたが近年の猛暑で全く使わなくなった「リズム」ボタンから移植する。
リズムとは間欠動作のことで、扇風機でしのげていた過去は便利だった。
交換して動作確認。
ちゃんと動く。
古いので、形状、厚み、押し込み深さ等が同じ新しいタクトスイッチを発注して、到着後新品に交換。

で、気になる抵抗付近の焼け。(抵抗は一切焼けていない)
基板部分レジストのない反対側が黒くなっていて、動作させていると抵抗辺りの基板が確かにかなり熱い。
3kΩを二個並列、さらにそれらを3直列になるように配置。
熱を計算してこういうレイアウトにしているのだろう。
直流変換ぽいものは基板上にないので、あるいはLEDだけはICで直接駆動しているかもしれない。
計6個の抵抗は表示の数値と乖離なく、熱破壊することなくきているようで、このまま使うことにする。