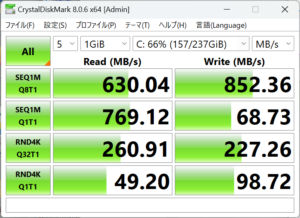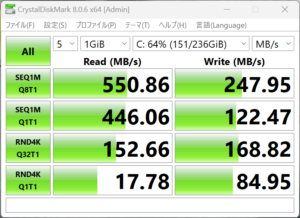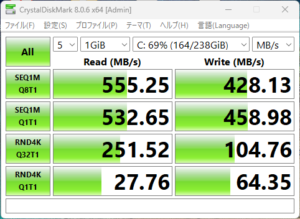windows11のエクスプローラが超くそ使えないのは以前書いた。
ファイルが多いとただ一覧表示するだけに1分くらいかかる。
ソートするとさらに倍かかる計算。
画像や動画ファイルは読み込みがめちゃ時間かかるし。
アドレスバーのツリー(パンくず)をクリックすれば、表示が固まったまま動かなくなる。
さらには動作が不安定で、表示フォルダを移動したにも関わらず古い場所を表示したまま。
だいたいこうなるとしばらくしてエクスプローラがクラッシュしてウィンドウが閉じられる。
windows10までを覚えていると、エクスプローラの件だけで考えてもアップして本当に損したと思っていた。
はよwindows12来い、と願っていた。
裏作w11め!
が、先日来た2024H2更新。
これを当てるとエクスプローラの挙動が早くなっている。
一覧表示、サムネイルなど、昔のようである。
超快適なのである。
普段はショートカットキーで操作するためそう不便ではなかったが、右クリックで出る絵文字だけのコピーや貼り付けの操作ボタンには言語表示が付された。
見にくいんだよ、絵文字表記のみは。
CUIとGUIを行ったり来たりしたものの、つまりは元に戻っただけである。
もうこのまま変な仕様変更はして欲しくない、windows11よ。
2024/12/20追記
ファイルのコピーや移動の進捗を表す進行バー?とでもいうのか、多少色が付いて以前よりマシになったのだが、w10より劣化したままな使い勝手。
あんな小さなプログレスバーではかなり見づらい。
ところで、同時進行で複数行った場合はどうなるのだろうか。
さてもう一点。
windowsメディアプレーヤー従来版をずっと使い続けているが、更新後「一つまたは複数のトラックをCDから取り込めません」と、読み込んでくれない。
ドライブが悪いのかと二つ試したが同じ結果。
今まで、一曲目だけ削除される謎現象、メディアフォルダ丸ごと削除される鬼畜現象などなかなかにキツい当たりをされても何十年と付き合ってきたのだが、この状況は初ではかなろうか。
タイミング的に24H2後で、疑わしいが、他に情報も無し。
具体的には、
「取り込んだ音楽を保存する場所」の「変更」が出来ない。(サーバのフォルダに指定していたが空欄のまま)
「音質」の変更を適用できずエラーとなる。
など。
CDをパソコンに取り込もうすると、「1つまたは複数のトラックを取り込めません」というメッセージが、出てきます。どのようにすればよいですか?
事象の数というか、もう使っている人そのものが少ないのかも知れない。
そもそもiPhoneのためにiTunesで取り込み、その保険としてwmpをサポートとして使っているわけで、その手段がないわけではないのだが…。
次回利用まで要経過観察である。
即再開。(おおうそである)
サーバじゃねぇか?ってことで調べてみたら。
[Windows11] 24H2更新後「組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲスト アクセスがブロックされている」と表示され共有フォルダにアクセスできない
「組織のセキュリティポリシーによって非認証のゲストアクセスがブロックされているためこの共有フォルダーにアクセスできません」または「エラーを特定できません」と表示される
gpedit.mscで解決である。(てことは無印w11では出来ないのか?不明)
読めなかったライブラリも読め、取り込みも無事出来た。