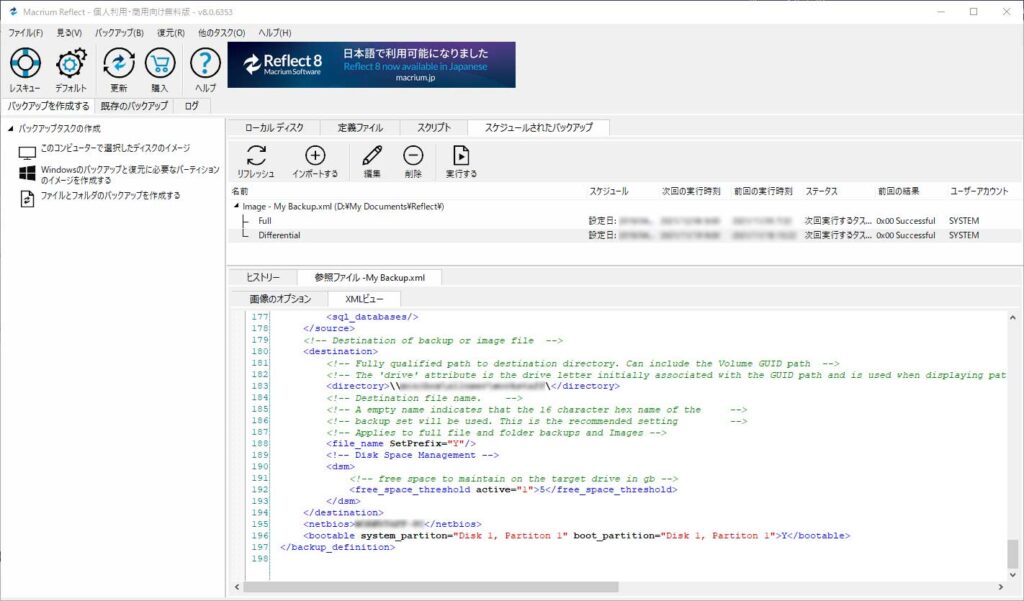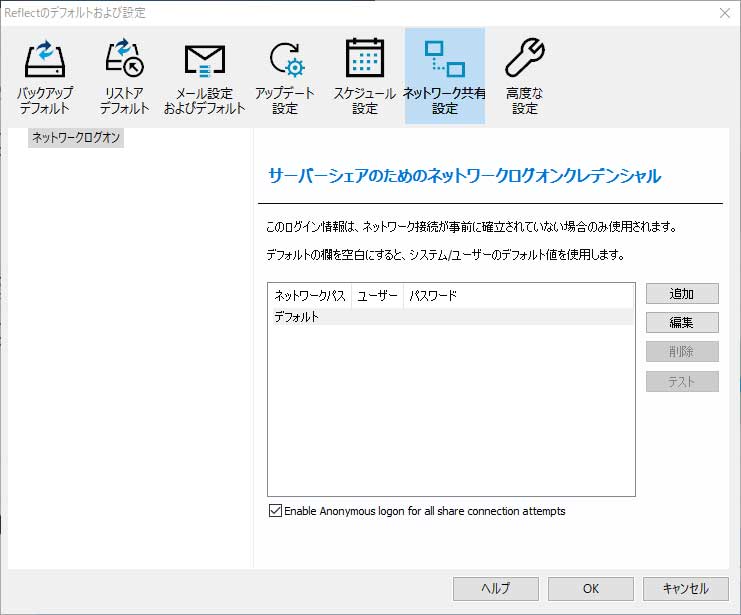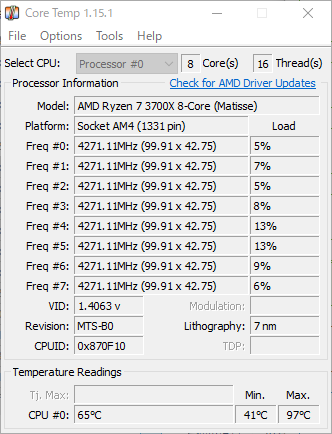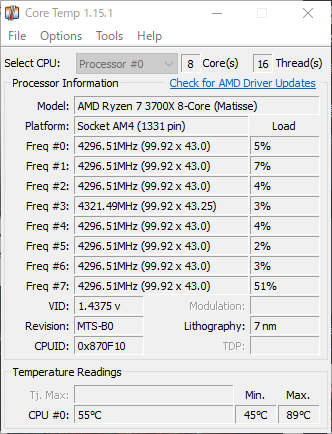Windowsが人気のショートカットキーTOP3を発表。2位は“Ctrl+Shift+T”、1位は?
ツイッターでwindows_japanがショートカットキーをつぶやいたそうで。
もう個人的には「cntl + x」 「cntl + c」 「 cntl + v」が圧倒的。
上記ですらすでにショートカットキーでコピペして書き換えている。
それとも、もしかしてこれらはショートカットキーですらないのか?
アドビが始まりだったか、編集にあっては、 「cntl + z」 「 cntl + shift + z」 も鉄板である。
これは特定のソフト内だけかもしれないが…。
最近は編集ソフトも多岐にわたり、上記と異なる(「やり直し」が大抵違う)ことが多いのだが、環境設定などで変更できるときは統一するようにしている。
「cntl + y」であることがたまにあるが、これってマウス操作と並列動作が無理じゃない?
ちなみにmacでのwindowsではこれらが機能しない?のか、そもそもあんまりmacのwindowsでは編集ソフトを使わないので調べもしないのだが、たまに使うと機能しなくて大変不便である。
キーボードの割り当てでなんとかなるのかも知れないが、きっとたぶんこのままスルー。