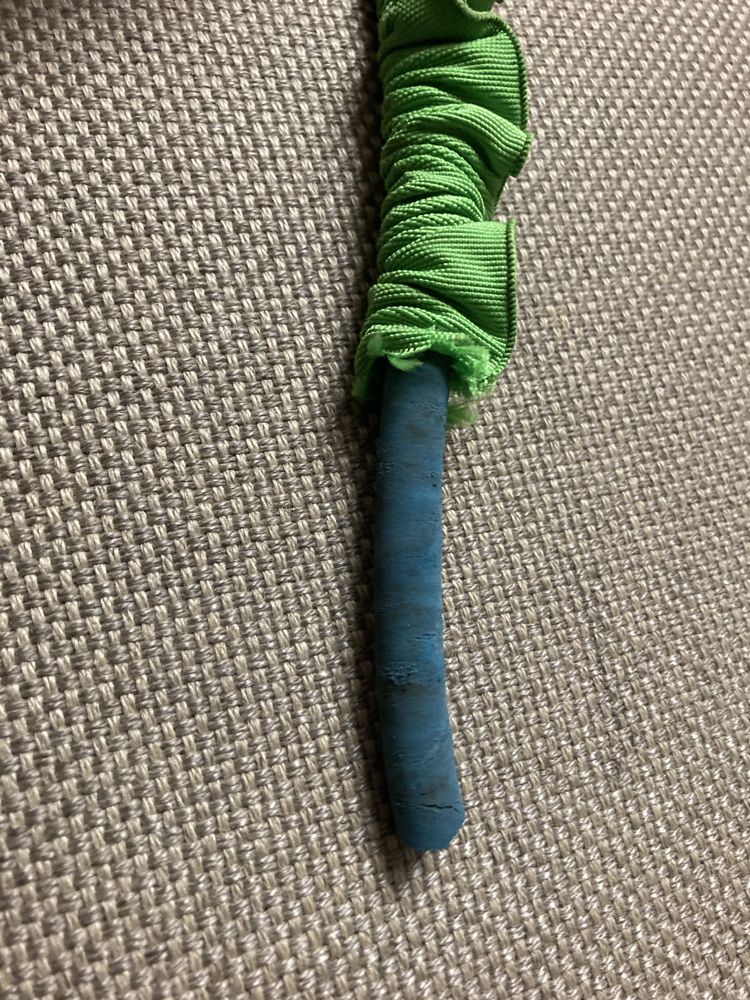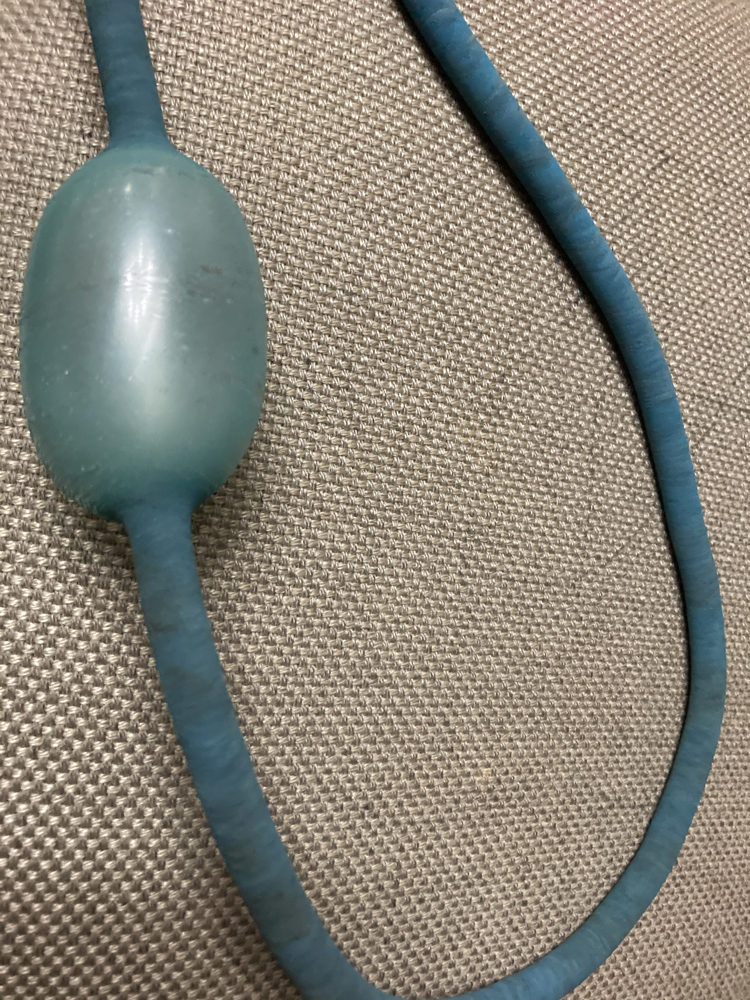下手な鉄砲というやつだろう、ひたすらフィッシングメールがやってくる。
ある時期を境にぐんぐん増えてきた印象。
推測であるが、迷惑メールの二重チェックをくぐり抜けるほどに誘い文句の日本語の精度が上がってきたため、と考えている。
確かに一見しただけでは迷惑メールだと読めないものが多くなってきた。
【警告】イオンカードユーザー必読!「イオンカード」を騙るフィッシング詐欺に潜入したらクオリティがヤバすぎた
詐欺メールにクレジット各社をかたるものが多く、JCBとかVISAとか有名どころが多い。
そのなかでも、上記の記事のように、イオンカードのメールも来ていた。
イオンカードを持っていないのでわからないが、上記リンク先を見る限り、なかなかに見分けづらそうであり、アドレス確認をしない人でかつカード所有者なら一見しての判断は難しいかも知れないな。
それはともかく、その先の内容である。
偽情報を入れて試す、というものである。
これは確かにわかりやすい。
特に、コレだとスマホでも簡単に試せる真贋確認かもしれないと納得。
これ、私の場合はだいたいが変なアドレスだとアクセスしない。
通常、メールの中身をざっと流し見て即削除、である。
そのアドレスの先がどうなっているのか、自身で確認したことがなかったこと、試してみたことがなかったことに改めて気付かされた。
そういう点で、こういう記事は大変有用なのだと、目から鱗な発見だった。
てことで書いとく。